長野県ネットAccess信州発 >> 信濃路・史跡巡り−街道と宿場・中山道
中山道
徳川家康が慶長7年(1602年)に制定した五街道の一つで、江戸と京都を結ぶ約538kmの
街道である。東海道とともに江戸と京都を結ぶ最も重要な街道で、現在は信越線と中央線に
ほぼ沿った道程となっており、歩くと69継ぎ137里、約22日間の道のりだ。
街道である。東海道とともに江戸と京都を結ぶ最も重要な街道で、現在は信越線と中央線に
ほぼ沿った道程となっており、歩くと69継ぎ137里、約22日間の道のりだ。
 |
碓氷峠・峠町(軽井沢町) 上州路の碓氷峠を登り始めると、清冽な碓氷川の水源があり、あと100mほどで 碓氷峠の頂上だ。ここには上信国境の熊野神社がある。石段を下った向かいに峠町 の名残りの水沢家の黒い門構えがあり、その左隣にある名物力餅を売る茶店はその 水沢家の経営である。当時峠町には社家が40数戸あったが今は3戸のみしかない。 |
 |
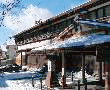 |
軽井沢宿(軽井沢町) 軽井沢宿はその昔飯盛女(遊女)で評判の宿場町だった。そのため天保14年(1843年) で町の人口451人のうち男189人女262人と圧倒的に女性の数が多かった。 険しい碓氷峠越えを終わりのんびりと休む人が多かったのだろうか。宿場町の入口 にあたるところ右手に休み茶屋だった「つるや」があるが今は旅館になっている。 |
 |
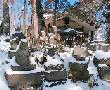 |
沓掛宿(軽井沢町) 沓掛宿の手前にある長倉神社は江戸時代の建築だが、この裏手には芝居などで評判 の沓掛時次郎の碑がある。宿場町はほとんど昔の面影を残さないが、駅前通りを横 切り少し行くと右手角地に本陣跡があるが古い建物が残るだけだが、ここには江戸 に降嫁される和宮が泊り、飲まれる水を汲んだという井戸が裏庭にある。 |
 |
 |
追分宿(軽井沢町) 碓氷峠の険路を登って信州に入る中山道は浅間山麓の軽井沢、沓掛、追分を「浅間 三宿」といって、飯盛女も大勢かかえ賑やかな宿場だった。その一つ追分宿には脇 本陣の「旅館油屋」や枡形の「つがるや」や右に行けば越後に向かう北国街道、左 に行けば京への中仙道の「分去れ」の道中碑が今も残っている。 |
 |
 |
小田井宿(御代田町) 天保14年(1843年)の記録では家数107軒に対し、旅篭屋は僅かに5軒にすぎ ない寂しい宿場であった。そのため宿場の繁栄をはかろうとして旅篭屋に飯盛女を 置くことを何度か試みたがその都度追分宿の強い反対にあって実現しなかった。国 道や信越線から離れていたためひなびた宿場の姿が残っている。 |
 |
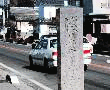 |
岩村田宿(佐久市) 岩村田の本町を中心に南北に延びる岩村田宿は近代化した商店街になり宿場の面影 が見られないが住吉町付近に多少残る。記録によると本陣と脇本陣がなく中宿と下 宿と問屋が一軒づつあった。しかし佐久甲州街道の北の起点、善光寺道の脇道とし て利用者は多かった。 |
 |
 |
塩名田宿(浅科村) ここには2軒の本陣があり、その一つ町の中南部にあった丸山善兵衛本陣だが、今 は屋根も改修され昔の面影は失われてしまった。もう一軒の本陣は妻入り切妻造り の豪壮な構えで昔を十分に偲ばせる。町の西外れを流れる千曲川の風景も見所の一 つ。中津橋の北30mほどの塩名田側の堤近くの川原に大きな舟つなぎ石がある。 |
 |
 |
八幡宿(浅科村) 八幡(やはた)宿に入ると、すぐ右手に鳥居が見えるが、この神社が宿場町の名の起 こりとなった八幡神社だ。貞観元年(1843年)滋野貞秀の創設と伝えられている。こ こから数10m程先の右手の表門は本陣だった小松家宅で文化元年建築の面影を十分 に残している。更に西に行った信号機下にあるのは脇本陣と問屋を兼ねた依田氏宅だ。 |
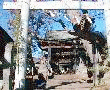 |
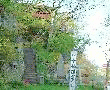 |
望月宿(望月町) 昔この辺りの牧から毎年8月15日(もちのひ)に朝廷に馬を献上したところから望 月の名が付いたという。御牧ヶ原の山麓に発展した望月には、いまも出桁式の造り や卯建を残す家並みが続くが、町の中心部にある脇本陣兼問屋の鷹野屋は京風の建 物にその面影を残す。また少し西寄りの大和屋は旅篭で国の重要文化財になっている。 |
 |
取材していない地域
・金山坂と瓜坂(望月町)・茂田井宿(望月町)・芦田宿(立科町)・長窪宿(長門町)・和田宿(和田村)
長野県ネットAccess信州発 >> 信濃路・史跡巡り−街道と宿場・中山道